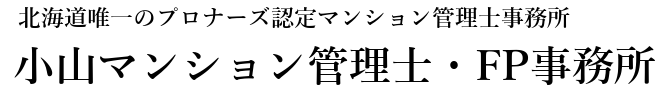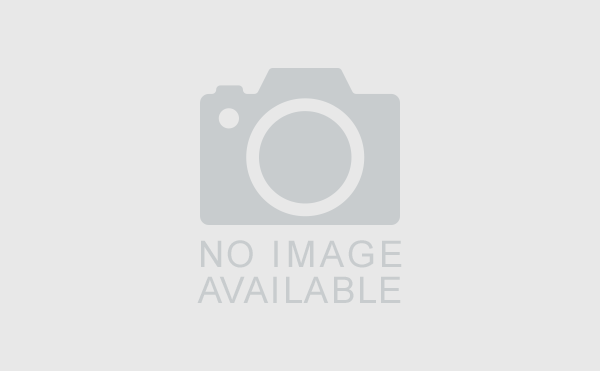最近、札幌市内のマンションから本当によく聞く声があります。
「理事長をやってくれる人が誰もいないんです…」
「もうみんな高齢で、輪番制にしても順番が回らない」
えっ!?理事長がいないマンション?と思うかもしれませんが、
これは今、全国的に進行している“理事長不在マンション問題”なんです。
この記事では、
そんな深刻な課題に対して注目されている新しい制度、
「外部管理者方式(総会監督型)」についてわかりやすく解説します。
🕰 第1章 マンションの「二つの老い」がやってきた
マンションは「建物」と「人」の両方が老いていきます。
これを私はよく、“二つの老い”と呼んでいます。
① 建物の老い
築30年、40年を超えるマンションでは、
配管・防水・外壁などの劣化が進み、
大規模修繕工事や設備更新が避けられません。
② 住民の老い
そして、もっと深刻なのが住民の高齢化です。
かつて若い家族だった住民も、いまや70代・80代。
理事会に出ることすら体力的に厳しいという方も増えています。
😓 第2章 理事長がいないとマンションは動かない
分譲マンションは「区分所有法」という法律に基づき、
理事会を中心に運営されています。
理事会のトップである理事長は、次のような重要な役割を担います。
- 管理会社との契約や修繕工事の発注を決裁
- 管理費や修繕積立金の出納を監督
- 総会の議案書を作成し、区分所有者に説明
つまり、理事長がいなければ、
マンションの運営そのものがストップしてしまうのです。
しかし現実には――
「パソコンが苦手で議事録を作れない」
「銀行への署名や押印が難しい」
「責任が重くて引き受けたくない」
といった理由で、理事長を引き受ける人がいないマンションが増えています。
🚨 第3章 理事長不在のリスクは想像以上
理事長が不在のまま時間が過ぎると、
マンション運営には次のようなリスクが生まれます。
- 管理会社との契約更新ができず、委託業務が止まる
- 修繕工事の発注や支払いができない
- 銀行口座が凍結され、積立金を引き出せない
- 住民間で責任のなすり合いが起きる
最悪の場合、「機能不全マンション」に陥ります。
札幌市でも、
「高齢化が進んで理事会が開けない」「理事長が辞めたまま次が決まらない」
といった相談が、ここ数年で急増しています。
💡 第4章 新しい解決策!「外部管理者方式」とは
そんな中で、国土交通省が推奨している新しい仕組みが、
「外部管理者方式(総会監督型)」です。
これは、理事長や理事会を置かずに、
第三者(=外部の専門家)をマンションの管理者に選任する方法です。
外部管理者は、法律上の「管理者」として、
以下のような職務を行います。
- 管理会社との契約や工事発注など、理事長の権限を代行
- 管理費・修繕積立金の収支を管理
- 総会の運営をサポートし、住民に説明
そして、外部管理者の業務は総会が監督します。
これが「総会監督型」と呼ばれる所以です。
🧑💼 第5章 外部管理者には誰がなるの?
この外部管理者として最も適任なのが、
私たちマンション管理士です。
マンション管理士は、国家資格を持つ管理の専門家で、
次のような知識とスキルを備えています。
- 区分所有法・標準管理規約などの法令知識
- 管理会社・理事会・住民の間に立つ調整力
- 修繕計画・会計・保険などの専門知識
外部管理者となることで、
理事長の代わりに実務を担い、
中立的な立場でマンションを適正に運営します。
🔧 第6章 外部管理者・総会監督型のメリット
では、外部管理者方式を導入するとどんなメリットがあるのでしょうか。
✅ ① 高齢化マンションでも運営が止まらない
理事長がいなくても、外部管理者が実務を担当します。
役員を引き受ける負担が軽減され、安心して暮らせます。
✅ ② 公平で透明な運営ができる
マンション管理士が中立の立場で運営するため、
特定の住民に偏ることのない、公平な管理が実現します。
✅ ③ 専門知識による質の高い判断
修繕や保険、法改正など、複雑なテーマにも迅速に対応できます。
札幌市のように寒冷地特有の設備管理にも柔軟に対応できます。
✅ ④ 総会での監督により民主性も確保
「外部に丸投げ」ではなく、最終決定権はあくまで総会にあります。
住民は監督・承認する立場として関与し続けます。
⚙️ 第7章 外部管理者方式の導入手順
外部管理者方式を導入するには、
次のような手順を踏む必要があります。
- 管理組合で導入検討(理事会や専門委員会で協議)
- 管理規約の変更(外部管理者を置く条項を追加)
- 総会での特別決議(区分所有者・議決権の4分の3以上)
- 外部管理者との契約締結
- 管理業務の移行・運営開始
規約変更や手続きには専門的な知識が必要なため、
最初の段階からマンション管理士に相談するのが安心です。
🧭 第8章 札幌市のマンションにこそ外部管理者が必要な理由
札幌市は、全国の中でも特に高齢化マンション率が高い都市のひとつです。
寒冷地特有の設備(ボイラー・配管・融雪装置など)を抱え、
維持管理の難易度が高いことも影響しています。
そんな中で、
「理事会が開けない」「理事長の後任が見つからない」
という相談は年々増えています。
しかし外部管理者制度を活用すれば、
プロが理事長の役割を担い、
マンションの法的・実務的なリスクを最小限に抑えることができます。
まさに、高齢化マンションにこそ最適な未来の管理モデルと言えるでしょう。
🌱 第9章 “管理を手放さずに委ねる”という発想
外部管理者方式は、「自分たちのマンションを手放す」ことではありません。
むしろ、
「自分たちではできない部分を、専門家に安心して委ねる」
という新しいかたちの自主管理なのです。
総会がしっかり監督し、意思決定を行うことで、
住民の意見はきちんと反映されます。
🔍 第10章 まとめ:いまこそ外部管理者を活用しよう
- 理事長不在は、マンション機能不全の危険信号
- 外部管理者方式(総会監督型)は、国交省も推奨する新しい管理形態
- マンション管理士が理事長の代行を担うことで、安心・透明な運営が可能
- 札幌市の高齢化マンションには特に有効
💬 最後に
「もう誰も理事長をできない…」
そんな声が出たときこそ、外部管理者方式の導入を検討するタイミングです。
マンション管理士は、外部管理者としてだけでなく、
制度設計・規約改正・総会サポートまでトータルで支援できます。
札幌市で理事会運営や役員不足にお悩みの方、
ぜひ一度、マンション管理士に相談してみてください。
👉 マンションの未来を守るのは、“任せる勇気”です。
外部管理者という新しい選択で、あなたのマンションを次の時代へ。