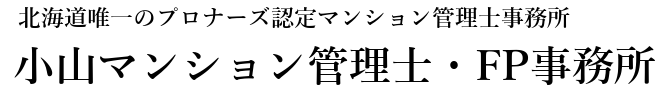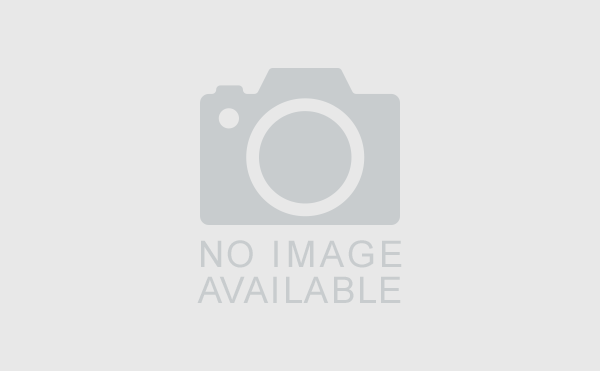地震や火災、台風など、自然災害や事故はいつ起こるか分かりません。 マンション管理組合にとって、防災体制の整備は“命を守る社会貢献”でもあります。でも、「何から準備すればいい?」「訓練はどう進行すれば?」と悩む理事の方は多いはず。今回は、札幌市のマンションで実践できる、防災訓練の基本ステップと実施の秘訣を分かりやすくまとめました。
🧱 目次
- なぜ防災訓練が必要なのか?
- コアメンバーは防火管理者、その周りを理事会で支える体制づくり
- 実施ステップ:計画→訓練→振り返りの流れ
- 高齢者や子連れ世帯へ配慮した工夫
- 最終的に:マンション管理士を活用しよう!
1. なぜマンションで防災訓練が必要なの?
- 住民間の連携不足は緊急時の混乱を招く
- 避難方法や連絡手段を共有するだけで被害が減るケースは多い
- 建物が密集している札幌市中心部や寒冷地では、適切な備えなしでは対応が難しい
- 管理規約や関係法令でも防災体制の整備を求める例が増えている
🎯 防災訓練は、「集団として備える力」を住民と理事会で醸成する初めのステップです。
2. 誰が仕切る?防火管理者と理事会の役割分担
✅ 防火管理者が中心になるべき理由
- 消防法などで指定される「防火管理者」は、初期消火や避難の責任を担う存在
- 消防署連携、消火器・非常用設備の確認、避難誘導手順の策定はこの人を中心に行うのが理想
✅ 理事会の役割
| 役割 | 具体内容 |
|---|---|
| 計画支援 | 日時・参加呼びかけ・避難計画案の承認 |
| 資料提供 | マンション案内図・非常連絡網の共有 |
| 住民説明 | 事前告知・住民への意義説明 |
➡️ 理事会と防火管理者が協働して訓練体制を運営する流れを最初に整えておくことで、住民が充実した備えを共有できます。
3. 防災訓練の基本ステップ:Plan・Do・Check を回す
✅ ステップ①:計画(Plan)
- 訓練内容:初期消火訓練・避難誘導・緊急連絡訓練など
- 日程:住民参加しやすい平日夕方や休日午前中
- 案内:掲示板・メール・ポスターなど複数媒体で周知
- 情報整理:建物案内図・避難経路マップ・連絡一覧表を準備
✅ ステップ②:実施(Do)
- 訓練開始の合図 → 住民が扉を閉めて集合
- 初期消火訓練(模擬消火器で体験)
- 避難誘導訓練:エレベーターを使わず階段移動
- 安否確認訓練:住民名簿活用、班ごとチェック
✅ ステップ③:振り返り(Check)
- 理事会で訓練後の振り返り会を実施
- 成功点と反省点を明記した報告書を作成
- 次回訓練への改善点や追加設備案を整理し、年間計画に反映
4. 高齢者や子連れ世帯への配慮を忘れずに
- 階段利用が難しい高齢者向け:避難支援グループを設定
- 子ども連れ家庭への配慮:ベビーカー対応の避難経路確保
- 寒冷地である札幌市特有の備え:暖房対応や防寒対策を事前に共有
➡️ 災害現場では、「誰も取り残されない」配慮が住民の命を守ります。
✅ 5. 管理士活用で防災体制の質をワンランク上へ!
✅ 管理士が提供できる支援内容:
| 支援内容 | 効果 |
|---|---|
| 年次防災計画表の設計 | 年間スケジュール化して備えを習慣に |
| 訓練プログラムの作成 | 訓練内容を体系化し、安全かつ効果的に実施 |
| 住民への説明資料作成支援 | 情報の見える化で参加率アップ |
| 防災資機材の選定サポート | 消火器・照明・連絡ツールの最適選定 |
| 緊急時のガバナンス体制整備 | 避難マニュアル・連絡手順の整備で混乱防止 |
📌 まとめ:災害時「できる準備」が、安心と信頼を作る
- 防火管理者+理事会で、住民の安全を守る連携体制を整える
- 訓練を通じて、「やり方を知っている」「顔が分かる」状態を日常化する
- 住民の幅広いニーズに応えつつ、避難訓練を続けることで「行政からの信頼」も築く
- マンション管理士を活用すれば、制度設計から運営支援まで一気通貫で支えられる
📣 札幌市のマンション管理組合・理事会の皆さまへ
「災害が起きたとき、大丈夫かな…」という不安を抱える理事の方は多いはず。
でも、防災体制は一人で作る必要はありません。
マンション管理士が、あなたの組合の「安心できる備え」を一緒に構築します。
ぜひお気軽にご相談ください。命を守る備え、間に合っていますか?