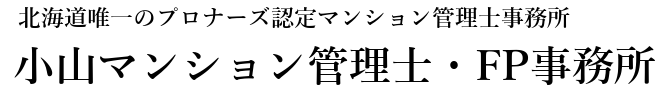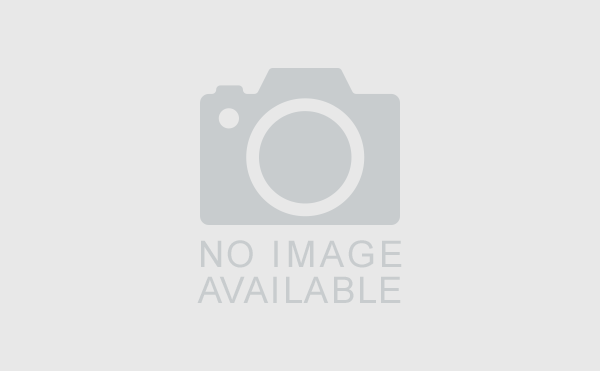◆ はじめに
「理事会を解散できるって本当なの?」
「外部管理者管理方式って聞いたけど、どういう仕組み?」
マンションの理事会運営に悩んでいる管理組合の方から、最近こうしたご相談をいただく機会が増えてきました。特に札幌市のように居住者の高齢化が進み、役員のなり手不足が深刻化している地域では、理事会の存続そのものが課題となっています。
そこで注目されているのが「外部管理者管理方式」です。
今回はその中でも「総会監督型」と呼ばれる仕組みについて詳しく解説し、成功のために必要なポイントを考えていきましょう。
◆ 外部管理者管理方式とは?
通常、マンションは区分所有者の中から理事会を組織し、理事長を中心に管理業務を遂行します。
しかし近年では、
- 理事のなり手不足
- 高齢化による役員業務の負担増
- 専門性不足による不安
といった理由から、理事会の運営が困難になっているマンションが増加しています。
そこで登場したのが「外部管理者管理方式」。
これは理事会を設置せず、外部の専門家や法人が管理者としてマンションを運営する方法です。
◆ 総会監督型とは?
外部管理者管理方式の中でも注目されているのが「総会監督型」。
これは、
- 理事会を完全に解散
- 外部管理者(専門家や管理会社など)が日常の管理を担当
- 区分所有者は総会で外部管理者を監督する
というシンプルな仕組みです。
従来の「理事会方式」よりも役員の負担が減り、管理の専門性が高まるメリットがあります。
◆ 管理会社が外部管理者になる場合
実際の運用例としては、管理会社がそのまま外部管理者になるケースもあります。
ただしここで大きな課題が浮上します。
- 管理会社は業務を「受託する側」であり、監督される立場でもある
- 外部管理者になると「監督されるべき立場が、自ら監督する側にもなる」という矛盾
- 実際の透明性やガバナンスの確保がまだ十分に検証されていない
つまり、実態がまだ見えていない方式だと言えるのです。
◆ マンション管理士が外部管理者になるのが理想
こうした課題を踏まえると、外部管理者にはマンション管理士のような第三者専門家が就任するのが理想的です。
マンション管理士は、
- 区分所有法や建築知識など幅広い専門性を持つ
- 利益相反を避けやすい
- 管理組合の立場でアドバイスできる
という特徴があります。
しかし、ここにも注意すべき課題が残されています。
◆ 利益相反と透明性の問題をどうクリアするか?
マンション管理士が外部管理者を務める際に最大の課題となるのは、利益相反と透明性の確保です。
たとえば、
- 管理者として業務を行いながら、別の立場でコンサルティング契約を結ぶ場合
- 工事業者選定で公平性を保てるかどうか
こうした問題をクリアするには、
- 契約内容を明確に定めること
- 報酬体系を透明化すること
- 複数の監事を置き、総会が厳格に監督する仕組みを設けること
が不可欠です。
◆ 総会監督型を成功させる3つの秘訣
では実際に「総会監督型」を成功させるためには、どのような工夫が必要でしょうか?
① 区分所有者の理解と合意形成
理事会を解散するという仕組みは、居住者にとって大きな変化です。
そのため、十分な説明と合意形成がなければ不信感を招きかねません。
説明会や勉強会を重ね、区分所有者全員が納得できる形で導入を進めましょう。
② 中立性の高い外部管理者を選ぶ
外部管理者には、管理会社ではなく独立した専門家を選ぶことが理想です。
特にマンション管理士であれば、中立性と専門性を兼ね備えており安心です。
③ 監事制度を強化する
総会監督型の弱点は、監督が形骸化しやすいこと。
そこで、複数名の監事を選任し、業務をしっかりチェックする体制を整えることが重要です。
◆ 札幌市で外部管理者方式が注目される理由
札幌市では、
- 高齢化による役員のなり手不足
- 冬季の除雪対応や修繕工事の特殊性
- マンション数自体の増加
といった事情から、外部管理者方式の導入を検討する組合が増えています。
しかし、まだ新しい制度のため、導入と運営には専門家の支援が欠かせないのが現状です。
◆ まとめ:専門家とともに安心の管理を
「理事会を解散できるなんて本当に大丈夫?」
そう思われる方も多いでしょう。
外部管理者管理方式は、確かに理事会の負担を大幅に減らし、管理の専門性を高める可能性を秘めています。
しかし、
- 管理会社が外部管理者を兼ねる場合の利益相反
- マンション管理士が担う場合の透明性確保
- 区分所有者の理解不足
など、乗り越えるべき課題も少なくありません。
だからこそ、導入を検討する際にはマンション管理士のサポートを受けることを強くおすすめします。
札幌市でもすでに導入を検討するマンションが増えている今、ぜひ専門家と一緒に安心の仕組みを作り上げていきましょう。