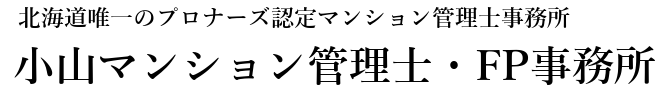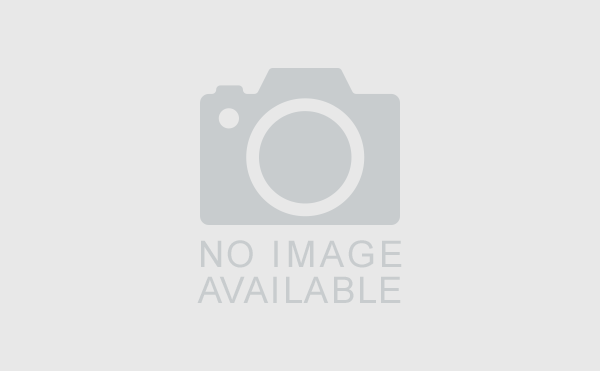◆ はじめに
「理事会の負担が重すぎて限界…」
「役員のなり手がいない、どうしたらいいの?」
こうした声が、札幌市をはじめ全国のマンションから聞こえてきています。特に高齢化が進むマンションでは、役員の担い手不足が深刻化しており、管理組合の運営そのものが危機に陥るケースも少なくありません。
そこで注目されているのが 「外部管理者管理方式」。
かつては「第三者管理方式」という言葉が使われていましたが、現在では「外部管理者」という呼び方に統一されつつあります。
なぜこの言葉の変更が必要だったのか?
そして「外部管理者管理方式」を成功させる秘訣はどこにあるのか?
今回はそのポイントを、マンション管理士の視点から解説します。
◆ 「第三者管理」と「外部管理者」の違いとは?
まず押さえておきたいのは、言葉の違いです。
以前は「第三者管理」という言葉がよく使われていましたが、この表現は 「管理会社も第三者に含まれるのでは?」 という誤解を招きやすいものでした。
しかし実際には、管理会社は管理組合との契約関係にある「業務受託者」であり、独立した第三者とは言えません。
そこで現在は、管理会社を含まず、区分所有者以外の外部の人物が管理者となる仕組みを指して「外部管理者管理方式」と呼ぶのが正式となっています。
◆ 外部管理者管理方式とは?
通常の管理方式では、区分所有者から選ばれた理事会がマンションを運営します。
しかし外部管理者方式では、
- 理事会を置かない
- 外部の専門家(例:マンション管理士)が「管理者」として業務を遂行する
- 区分所有者は「総会」でその業務を監督する
という体制をとります。
この中でも「総会監督型」と呼ばれる方式が、最も注目されています。
◆ 総会監督型のメリット
- 役員の負担がゼロに近くなる
理事会が解散されるため、役員を担う必要がなくなります。 - 専門性の高い管理ができる
法律・建築・会計などに精通した専門家が管理を担当します。 - 意思決定がシンプルになる
区分所有者は総会で管理者の業務をチェックする仕組みなので、責任の所在が明確です。
◆ 外部管理者にマンション管理士が最適な理由
外部管理者を誰にお願いするのかは非常に重要なポイントです。
管理会社がそのまま外部管理者になる例も考えられますが、
- 管理業務を受託している立場と、監督される立場が重なってしまう
- 利益相反のリスクが高い
という問題があります。
一方、マンション管理士は独立した立場で、管理組合の利益を第一に考えられるため、外部管理者として理想的な存在と言えます。
◆ 利益相反と透明性の問題
ただし、マンション管理士が外部管理者になる場合にも、避けて通れない課題があります。
それが 利益相反と透明性の確保 です。
例えば、
- 外部管理者として業務を行いながら、別途コンサル料を受け取る
- 修繕工事の業者選定に影響を与えてしまう
といった状況が起こりうるのです。
これを防ぐには:
- 契約内容の明確化
報酬・業務範囲を文書化し、住民が理解できる形に。 - 情報公開の徹底
決算や業務報告はわかりやすく、かつ定期的に総会へ提出。 - 監事制度の強化
総会が形骸化しないよう、複数の監事を選任し、外部管理者の業務をチェック。
これらの仕組みが整えば、安心して外部管理者を任せられる体制になります。
◆ 総会監督型を成功させる3つの秘訣
外部管理者管理方式の導入を成功させるためには、次の3つが欠かせません。
① 区分所有者への丁寧な説明
理事会をなくすという大きな変化には、不安や抵抗も生じます。
住民説明会や個別相談を重ね、理解と合意形成を十分に行うことが必要です。
② 中立的な外部管理者の選任
外部管理者は誰でもよいわけではありません。
管理会社ではなく、マンション管理士のように独立した専門家を選ぶことが、信頼性を高める近道です。
③ 総会と監事による監督体制
総会は単なる形式ではなく、外部管理者を監督する重要な場です。
監事の役割も強化し、二重三重のチェック体制を築くことで透明性が守られます。
◆ 札幌市で外部管理者方式が注目される理由
札幌市のマンション事情は、外部管理者方式が求められる背景を強く映しています。
- 高齢化が進み、役員のなり手不足が顕著
- 雪害や除雪対応など、地域特有の管理課題
- 中古マンション市場の拡大により、管理の質が資産価値に直結
こうした現状から、外部管理者方式を導入する動きが少しずつ広がっています。
◆ まとめ:外部管理者方式は「万能」ではない
「第三者に任せて大丈夫なの!?」という不安は、もっともな疑問です。
外部管理者方式は、確かに理事会の負担を減らし、専門的な運営を可能にする新しい仕組みです。
しかし同時に、利益相反や透明性の問題といった課題も抱えています。
だからこそ、導入を検討する際には マンション管理士のサポート を受けることが不可欠です。
札幌市でも導入を模索するマンションが増えている今、ぜひ専門家と一緒に安心・安全な管理体制を築いていきましょう。